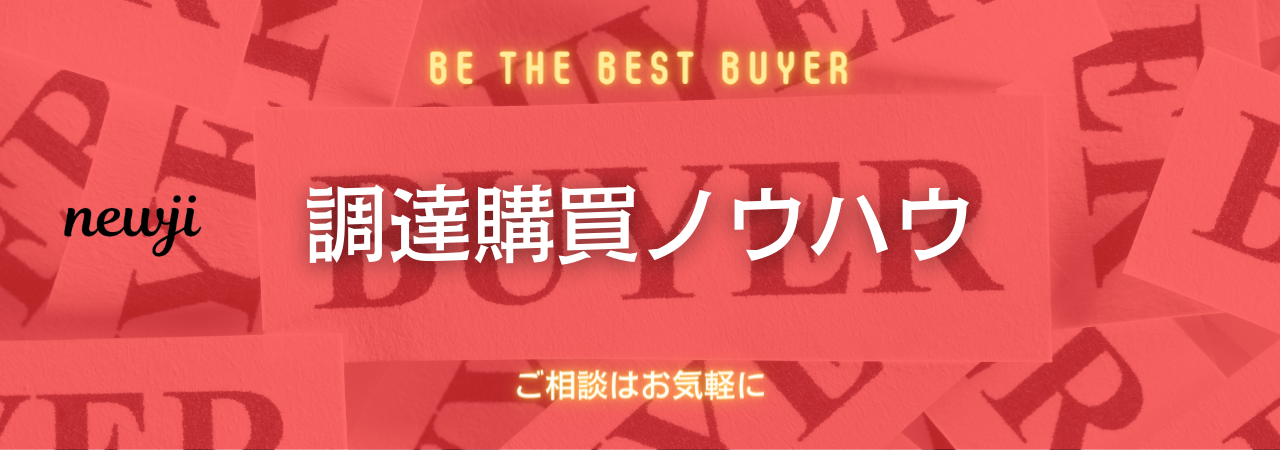- お役立ち記事
- コストアップがコストダウンになる?最終的なコストを比較しよう!
コストアップがコストダウンになる?最終的なコストを比較しよう!
今日は、3年間のトータルコストが値下げに頼らずとも、逆に値上げをしてでもコスト削減につながるということを3年間トータルコストで比較しながらお話ししたいと思います。

3年前、中国で取り組んだその一つに品質を向上させるために値上げをしてでも品質を維持しながら、でも最終的には一定の期間の中で支払い額を減らすという取り組みをしました。
実際には中国の場合、短年で成果を出さなければいけないということで1年間の中でコスト削減にならないとなかなか評価されなかったので、
新しい製品の開発ですとか、何年もかかるコスト削減の取り組みはどうしても後回しになっていました。
目次
備品、消耗品の品質でトータルコストダウン
それでもやらなければならないことってたくさんあって、まず最初に手を付けたのが製品というよりは備品、消耗品の類。
例えば工場では手袋、作業着、ヘルメット、マスク、安全靴などいろいろなものを身につけて仕事をしていますが、安く買うために品質の悪いものを使っていました。
その結果、買い替えの頻度が非常に激しく、なかなか支払い総額予算内に収まらないということが起きていました。
単価を下げれば予算内に収まるだろうと思っていたのが、耐久性が短くなってしまった結果、頻繁に買い換えることで1年間の予算を早期に食いつぶしてしまって、期中で足らない分は作業員が自己負担をしているということが起きていました。
これは値下げによるコストアップ、コスト削減にならずコストアップになっていました。
さらに品質にも影響が出ていました。
自分の給料からなんで必要なものを買わなければいけないのか、という不満から作業員のモチベーションも下がりました。
安全性にも問題があって手袋が破れるとか、作業着がほつれて引っかかるとか、安全靴に穴があくとか、このようなことが直接、怪我や事故につながるということが起きていました。
品質の悪いものを使いたくないという現場の声があり、購買としては同じ値段で良い品質のものを探していましたが、もう値下げに行きついてしまったところで基準を満たす、品質が満足いくものを手に入れるということはほとんど不可能に近い状態でした。
そこで役員を説得するために、単価は引き上げて品質を向上させることで買い替えの頻度を減らし最終的な支払い額を減らす、この支払い額が経ることで購入単価が上がっても品質が向上しても最終的なコスト削減になるということを図に書いて、説明して理解を得ました。
その図に関しては別途ご覧いただきたいと思います。
今よりも、5年後につながるコストダウン
幾つかのパターンがあります。
シミュレーションをしてすぐに買い替えなければいけないものとか、何年もの耐久性があり買い替えの頻度が少ないものとか、
買い替え頻度をどれくらいに設定するかによって、3年間〜5年間でどれだけのコストがかかるかということを推定して企画をしてみました。
実際にその通りになるかどうかというものが3年間終わってみないと分からないわけですけれども、1年間のうちで結果がでるもの、でないものとあるわけで、
結果が出ないものはどうしても後回しになっていました。
短期で結果の出るもので成果が上がれば2年、3年、5年と少しずつ時間とともに取り組まなければいけないものにも波及して取り組めるような環境になっていきました。
そこまでやるのに相当の時間がかかったわけで、かなり高いお勉強代ということになったわけですけれども、いずれにしても安かろう、悪かろうというのはコストアップになるだけではなく、安全性の問題だったり生産性の問題だったりといろんなところに悪影響があるかということを知ってもらった訳です。
知ってもらうためにはデータを取らなければいけなかったんですけど、それまでデータを取るということをしていませんでした。
現場で不満の声があってもじゃあ数値データで比較してどれだけ悪くなったの?良くなったの?お金がかかってるの?
というものが集計されていませんでしたのでなかなか役員を説得することはできませんでした。
ですので、そのデータを取るところから始めた訳です。
これが原材料や部品に話が及ぶまでには3年もかかったんですけれども、次に取り組んだのが消耗品。
例えばフィルターですとかエンジンオイルのようなもの、さらにはブレーキパッドのような結構交換の頻度が激しい摩耗するもの。
これについての耐久性は随分議論しました。
製品自体の耐久性がまだ日本製と比べて中国性はそれほど長くないということもあり、それだけの部品の耐久性を長くしてもしょうがないということで、
全ての品質のバランスを考えると検討した品目だけ高頻度、または長期に使うということが果たしてどれだけ意味があるんだろうかということにもなって当面は製品全体のバランスを見ながら徐々に耐久性を伸ばしていくという取り組みをしてきました。
自動車でも建設機械でも、その他の機会でもそうなんですけれどもいかにメンテナンスの頻度を減らすかによってその補修部品だとか消耗品、それの交換の人件費、その機械が止まっている間の利益損失を減らすことにつながります。
そういったものを考えると、耐久性が長い、消耗部品やメンテナンスの頻度が少ないということがどれだけコスト削減に繋がるかというものが見えてきます。
その結果を目で見るためにはデータをきちっと取らないといけません。
実際に販売した製品がどのように使われてどれだけの頻度でメンテナンスされているのか、部品交換や消耗品の追加などがされているかというデータをきちっと取らないと、それも2年、3年、5年と時間を積み重ねてデータを取らないと結果が出てきません。
単に丈夫で長いものと言っても具体的な数値がないとなかなか役員を説得できないですし、お客様にも理解が得られません。
こういった取り組み、購買部門としては単に単価を安くすることだけがコスト削減でないという例をこれまでもお話ししましたし、これからもいろいろと他の例も示しながら解説をしていきます。
ぜひいろんな原材料、部品、消耗品の耐久性がどれだけ伸びるかでどれだけコスト削減になるか、どれだけ単価が上がってもトータルコストが下がるかということをシミュレーションし、それを実際に実行しデータを取って効果を測定するこれを是非やってほしいと思います。
今日は以上です。
 資料ダウンロード
資料ダウンロード
QCD調達購買管理クラウド「newji」は、調達購買部門で必要なQCD管理全てを備えた、現場特化型兼クラウド型の今世紀最高の購買管理システムとなります。
 ユーザー登録
ユーザー登録
調達購買業務の効率化だけでなく、システムを導入することで、コスト削減や製品・資材のステータス可視化のほか、属人化していた購買情報の共有化による内部不正防止や統制にも役立ちます。
 NEWJI DX
NEWJI DX
製造業に特化したデジタルトランスフォーメーション(DX)の実現を目指す請負開発型のコンサルティングサービスです。AI、iPaaS、および先端の技術を駆使して、製造プロセスの効率化、業務効率化、チームワーク強化、コスト削減、品質向上を実現します。このサービスは、製造業の課題を深く理解し、それに対する最適なデジタルソリューションを提供することで、企業が持続的な成長とイノベーションを達成できるようサポートします。
 オンライン講座
オンライン講座
製造業、主に購買・調達部門にお勤めの方々に向けた情報を配信しております。
新任の方やベテランの方、管理職を対象とした幅広いコンテンツをご用意しております。
 お問い合わせ
お問い合わせ
コストダウンが利益に直結する術だと理解していても、なかなか前に進めることができない状況。そんな時は、newjiのコストダウン自動化機能で大きく利益貢献しよう!
(Β版非公開)