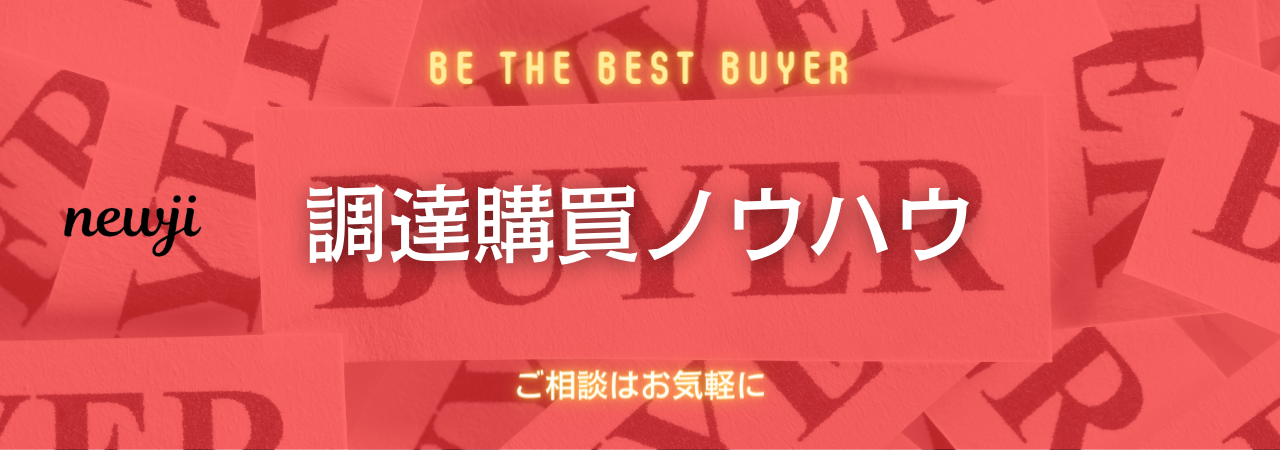- お役立ち記事
- 段ボールや印刷用紙、究極のコスト削減はペーパーレス!
段ボールや印刷用紙、究極のコスト削減はペーパーレス!
今日は紙の購買の話をします。紙製品、基本的には大きくいくつかに分かれます。
例えば梱包資材としての紙、段ボール、それからもう一つは印刷用紙としての紙。
例えばコピー用紙だとかA0、A1、A2のアート紙。例えば新聞の折り込みチラシだとか雑誌など様々な印刷物に使われる紙。
これについて今日はお話をします。
ペーパーレスでだんだん使用量が減っていく運命にある紙ですけれども、まだまだ使用量は多い品目です。
ごくわずかではありますが、製品に直接使われるものもあります。例えばフィルターなどは紙を使われるケースがあります。
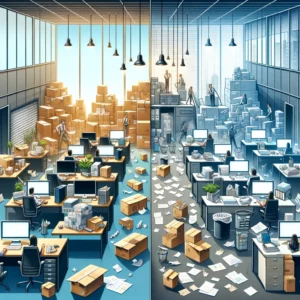
目次
ダンボール、梱包資材の購買コストはどう削減できるる?
まずは梱包資材としての紙についてお話をします。
例えば段ボールですけれども、様々な段ボールのサイズがあります。
断面積を見ると、波形コルゲートが間に挟まっていますが、これが強度を上げている仕組みになっています。
単純な平べったい板紙であれば折れ曲がってしまうところが、波形によって強度を保っています。
更にこれが二重構造、三重構造、滅多にないんですけれどもそういったもので強度を保たせる、軽くて丈夫なものとして使用されています。
森林資源の方だとか、再生利用の素材に梱包資材もどんどん切り替わっていくことによって、だんだんこの段ボールの使われる頻度は減ってはきてはいますけどまだまだ使用頻度が多いというのが現状です。
この段ボールの購買ですけれども、できるだけコスト削減をするために規格、日本工業規格とか世界の標準の規格を揃えていくということが大事なんですけれども、実際には色んなサイズがある中で運送効率、積載効率を考え、できるだけその中に収めることも必要になっていきます。
どういうことかと言うと、例えばトラックの積載効率、高さ制限、車幅制限、長さ制限この中にぴたっと収まるようなサイズを探します。
まずは段ボールの箱を積み重ねてパレットに乗せ、そのパレットでフォークリフトで上げ下げをする。
このパレットに載せた段ボールの箱がたまに入る、コンテナに入るいろんな制限があってどれだけ積載効率が上がるかっていうことを考えても、どうしても製品そのもののサイズや容量というものがあって自由にはなりません。
製品があっての梱包資材ですが、できるだけ積載効率を上げるために、逆に製品のサイズを変えるということも起きています。
例えば飲料メーカーの生産する炭酸飲料、ビールやジュースなどは色んなサイズがありますが、まずは容量が決まっています。
何ミリリットルっていうのは決まっています。それに合わせて缶のサイズが決まります。
例えば6本入り、12本入り、1ダースとか半ダースとか。
サイズが決まるとできるだけ効率よく購入するために各メーカーがバラバラでオーダーしていたものを一緒に、複数のメーカーが共同でダンボールのメーカーに買う。
生産を依頼する共同購買な発想ですけれども、こういったことが最近行われつつあります。
逆にペットボトルの色んなデザイン性を重視して差別化を図りたいということをしてきた結果、メーカーごとでばらばらになってなかなか梱包資材も統一規格になりづらいというようなことも起きています。
何をもって最適とするか、まずは製品が売れなければ話になりません。
これから考えていかなければいけないのはどれだけ資源を有効活用し、少ないコストで梱包資材を減らすことができるかどうか、
さらにはコストを削減することができるかどうか、安全に製品を運べることができるかどうか、ということも考えていかなければいけません。
ペーパーレスの中行われるさらなるコスト削減
もうひとつのコピー用紙、印刷用紙ですが、どんどんペーパーレスが進んでいって生産量も減っています。
会議で使われるようになったコピー用紙なんかも今は逆にどんどんペーパーレスで電子化され、会議もエクセルやワードの資料をプリントアウトしてハンドアウトせず直接プロジェクターに投影し、資料はメールで送るなどというやり方が増えています。
紙に出さないということになる結果、紙の使用量もどんどんと減ってます。
更には新聞折込チラシなんかについても、私がBMWの時はかなり時間を割いてどれだけ安く買うか、A2コート紙をどれだけ製紙メーカーから大量に安く仕入れるかという話をしていました。
コスト削減のために紙の厚さや品質は保ちたい、グレードは下げたくないが購入金額を減らしたいということで、紙を薄くするという取り組みをしてみたり、印刷の効率を高めるためにロスを減らす、印刷機にぴったり合うサイズの紙を買うなどいろんな取り組みをしてきました。
直接製紙メーカーと話を何度もしてきたんですが、今このようなペーパーレス時代にあって印刷物や新聞、色んなものが電子化されて減っていく中、購買の条件もだんだん難しくなってきています。
ボリュームが減れば購入単価がだんだん上がっていく傾向にあるんですけれども、どちらかというと価格はまだまだ下がるところまで下がり着いたところまできつつあります。
実際には漂白を止めたり、少しずつ環境にやさしい再生パルプを使用したりといろんな取り組みをしていますが、これらはそれぞれ実はコストアップの原因です。
それでも環境優先のために取り組まなければいけない、だったら紙そのもの自体をやめてしまうっていうところまで来ています。
どれだけ紙をやめられるか、ペーパーレスにするかということになるんですけれども、
最初に話した段ボールは物を買えば必ず運ばなければいけない、その時にどれだけ梱包を簡易にするか、減らすか、再生利用のものに変えていくか、プラスチックコンテナに置き換えられるかということを考えていかなければいけない。
かつてはビールも瓶ビールの時代にはそれを運ぶプラスチックのコンテナ、折りたたみのコンテナといろんなものが再生利用されていましたが、缶ビールに置き換わってそれを運ぶ段ボールの使用量が増えたんです。
今後またこれがどのように推移していくか、購買の立場からいけばどれだけ紙の資源、古紙、再生紙を含めて今後需要が減っていくと思われます。
まだまだ紙の需要がなくなるまでに時間がかかると思うんですが、その中で共同購買ですとかグレードを変えるとかいろんなことでまだまだコスト削減の余地は残っています。
そういった詳しい話については、自分も何十年も紙に携わってきましたので、今後細かい話を別途していきたいと思います。
 資料ダウンロード
資料ダウンロード
QCD調達購買管理クラウド「newji」は、調達購買部門で必要なQCD管理全てを備えた、現場特化型兼クラウド型の今世紀最高の購買管理システムとなります。
 ユーザー登録
ユーザー登録
調達購買業務の効率化だけでなく、システムを導入することで、コスト削減や製品・資材のステータス可視化のほか、属人化していた購買情報の共有化による内部不正防止や統制にも役立ちます。
 NEWJI DX
NEWJI DX
製造業に特化したデジタルトランスフォーメーション(DX)の実現を目指す請負開発型のコンサルティングサービスです。AI、iPaaS、および先端の技術を駆使して、製造プロセスの効率化、業務効率化、チームワーク強化、コスト削減、品質向上を実現します。このサービスは、製造業の課題を深く理解し、それに対する最適なデジタルソリューションを提供することで、企業が持続的な成長とイノベーションを達成できるようサポートします。
 オンライン講座
オンライン講座
製造業、主に購買・調達部門にお勤めの方々に向けた情報を配信しております。
新任の方やベテランの方、管理職を対象とした幅広いコンテンツをご用意しております。
 お問い合わせ
お問い合わせ
コストダウンが利益に直結する術だと理解していても、なかなか前に進めることができない状況。そんな時は、newjiのコストダウン自動化機能で大きく利益貢献しよう!
(Β版非公開)