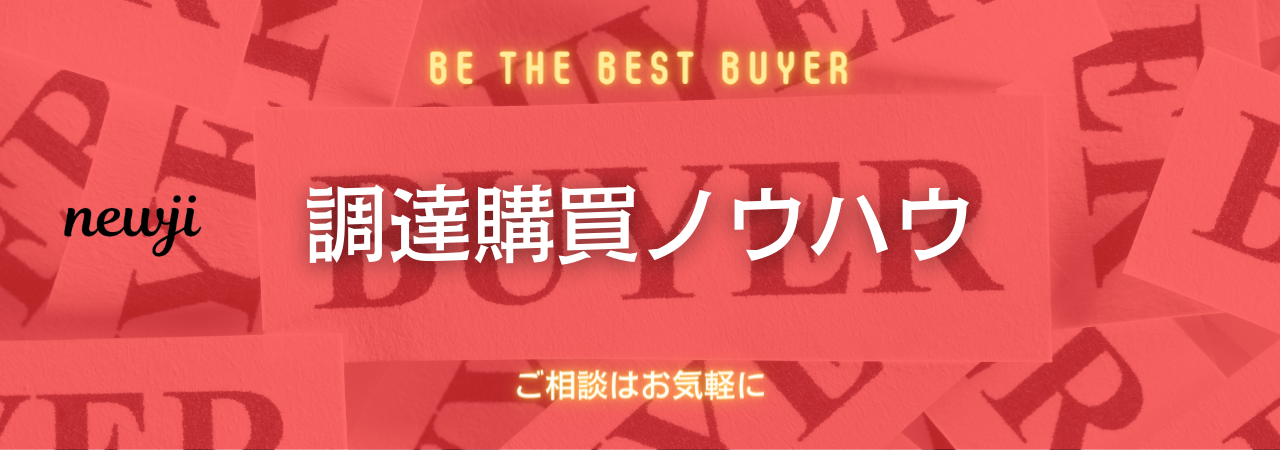- お役立ち記事
- どっちを優先する?品質と価格の交点を導き出す方法!
どっちを優先する?品質と価格の交点を導き出す方法!
今日は購買の中でもコストと品質のバランスについて少し詳しくお話をしたいと思います。
目次
品質と価格のバランス
品質と価格のバランスに関係について、縦軸を品質、横軸を価格としたときに
上に行けば行くほど品質が良くなり、右に行けば行くほど価格が高くなるということで
ちょうどその間にあるところがバランスが保たれていると言うことになります。
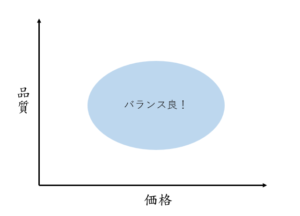
左下が低価格で低品質、右上が高価格で高品質。
上へ行くとだんだん値段も品質も高くなる、その時に割高かなというものと、
品質へ行けば安いけど、これって品質がいいな逆にこれ高いけど品質が悪いなというものがあると思います。
あくまでもこれは相対的な話になりますし低品質低価格、高品質高価格それぞれで受け入れられているものもあります。
例えば100均のものそれなりの品種ですがお値段もそれなり、高級ブランドは当然値段も高いですが品質もそれなりに良い。
例えば自動車だって軽自動車は安いですがそこそこの品質。日本製品だと壊れないということで高品質だったりしますけれども、海外輸入車のロースロイスとかポルシェとか値段が高くて品質も良いものももちろんあります。
必ずしも壊れやすい、壊れにくいはまた別の問題ですが、そういったものもあります。
良い品質とは
ではそれはどうやって決まってくるでしょうか。
実際には購買の仕事の中で高級品質のものを原材料調達として行う場合はそれなりの品質を選びます。
じゃあそれなりの品質ってどういう品質という風になるんですけれども、その製品の機能、性能、価値に見合った原材料、部品の調達になります。
低価格、低品質であれば耐久性もそこそこ、図面通りと言ってもミクロの単位の細かい話ではなくほぼ合っていればいいや、そこそこ使えればいいというものになってくるのでメーカーとの交渉も変わってきます。
自分が経験してきた電線会社、輸入自動車会社、建設機械会社で求められる品質と価格のバランスのいいところを比較するのはなかなか難しいので競合他社と比べるということをよくします。
できるだけ競合他社より少しでも安く売りたいとか、少しでも性能の良いものを売りたいとかというものが比較になってサプライヤーとの交渉になってきます。
長い時間使えるもの、例えば自動車でも建設機械でもそうですけれども保証期間、耐久年数は各社それぞれ似たようなところで評価されています。
それと比べてどれだけ優れてるのというのが比較の要素になってきます。
よく製品の比較をしますが購買部門で比較する場合は競合他社の原材料、部品。
どこから何を買っている?どのぐらいの値段で買っている?どのくらいの品質で買っている?
素材の純度だったり、部品の精密度とかいろんなもので比較した上でほぼ同等のものを少しでも安く買いたいっていうのが基本的な考え方になります。
購買が品質を考えるうえで大事なこと
もう一つ大事なのがどれだけ同じ品質のものを安く買うかということになります。
よく単に値段を安くしろという話がありますが、そこには求められている品質が同等であるという前提条件があります。
この品質を考えないで単に値段だけ下げようという交渉をすると品質も落ちてしまいます。
そのようなことが起きないようにするために、最低、守らなければいけない品質というのがあると思います。
その守らなければいけない最低基準の品質って何でしょうか。
図面通りに出来上がっているか、公差の範囲内にあるか、守られた環境基準、成分表示、いろいろな法的な条件を満たしているなど考慮すべきことはたくさんあります。
それを満たした上で後はどれだけ安くなるか競合他社よりも少しでも安く買いたいっていうのは購買の思うところですけれども、
もう一つ目標としては今売っている製品の変化を少しでも良くして利益を出したいことです。
その目標と比べてどれだけ安く買えるか、どれだけ品質を向上させるということになります。
どれだけ品質を良くしてなおかつ購入価格を安くするか、場合によってはどれだけ品質を維持しながら安くするか。
品質が悪い時にはどれだけ品質を上げながら価格を現状維持するか、場合にはもっと品質を高めたい。
耐久性が伸びるのであれば購入価格も高くしても良い、それでもいいというようなこともあります。
このように目指す方向性が価格を下げるのか、品質を向上させるのか、品質を向上させながら価格を下げるのか、時には品質を少し下げてでも大きくコストを下げたいのか、その時々の状況、競合他社の戦略や会社の事業方針によって変わってきます。
利益を出したいのか販売を拡大したいのか、品質を向上させて顧客満足度を上げるのかそれぞれ方向性が違います。
購買単独で決められることではありませんがお客様のために何をどうすればいいのかっていうことを考えながらサプライヤーと交渉するということになります。
続きはまたもう少し詳しく話をしていきたいと思います。
今日は以上です。
 資料ダウンロード
資料ダウンロード
QCD調達購買管理クラウド「newji」は、調達購買部門で必要なQCD管理全てを備えた、現場特化型兼クラウド型の今世紀最高の購買管理システムとなります。
 ユーザー登録
ユーザー登録
調達購買業務の効率化だけでなく、システムを導入することで、コスト削減や製品・資材のステータス可視化のほか、属人化していた購買情報の共有化による内部不正防止や統制にも役立ちます。
 NEWJI DX
NEWJI DX
製造業に特化したデジタルトランスフォーメーション(DX)の実現を目指す請負開発型のコンサルティングサービスです。AI、iPaaS、および先端の技術を駆使して、製造プロセスの効率化、業務効率化、チームワーク強化、コスト削減、品質向上を実現します。このサービスは、製造業の課題を深く理解し、それに対する最適なデジタルソリューションを提供することで、企業が持続的な成長とイノベーションを達成できるようサポートします。
 オンライン講座
オンライン講座
製造業、主に購買・調達部門にお勤めの方々に向けた情報を配信しております。
新任の方やベテランの方、管理職を対象とした幅広いコンテンツをご用意しております。
 お問い合わせ
お問い合わせ
コストダウンが利益に直結する術だと理解していても、なかなか前に進めることができない状況。そんな時は、newjiのコストダウン自動化機能で大きく利益貢献しよう!
(Β版非公開)