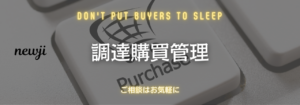- お役立ち記事
- 契約書に明記されていない取引慣行が紛争を招いた事例と予防策

契約書に明記されていない取引慣行が紛争を招いた事例と予防策

目次
はじめに:製造業の現場で起きる“見えないリスク”
製造業の調達・購買現場では、契約書が存在していても、実際の取引が円滑に運ぶとは限りません。
とくに日本のモノづくりの現場では、昭和時代から続く「暗黙の了解」や「口頭の約束」、いわゆる“取引慣行”が今も根強く残っています。
この目に見えない“暗黙のルール”が、時に想定外のトラブルを引き起こし、最悪の場合は相手企業との紛争や信頼関係の崩壊にまで発展してしまいます。
本記事では、実際の紛争事例をもとに、なぜ契約書に明記されていない“慣行”がリスクとなるのか、どうすればそれを未然に防げるのかを、現場での視点・実践ノウハウも交えながら深掘りします。
加えて、今後の製造業で求められる進化についても考察します。
これからバイヤーを目指す方や、サプライヤー側でバイヤーの本音を知りたい方、現場の管理職にとってもヒントになる内容をお届けします。
よくある“取引慣行”が紛争を招いた事例
納期変更トラブル:口頭合意が招いた納品遅延
ある大手機械メーカーと部品サプライヤーA社の事例です。
従来から両社は納期や仕様の変更について、電話やメールでやりとりし、双方の担当者間で「了解しました」と口頭で確認するだけで済ませていました。
ところがある時、大型の新規案件でメーカーから「納期を1週間前倒ししてほしい」と急な要請が入ります。
サプライヤーA社も「検討します」と曖昧な返事のまま、内部で調整しきれず結局当初約束通りの納期でしか生産ができませんでした。
しかしメーカー側は、「サプライヤーが納期変更に同意した」と認識しており、納品遅れとして大きなペナルティを科しました。
契約書には、納期やその変更に関するコミュニケーション方法や手続きがきちんと明記されていなかったため、口頭合意の有無を巡って双方が激しく対立し、訴訟寸前まで発展しました。
数量変更・発注キャンセルにまつわる紛争
自動車部品メーカーB社と精密加工業C社の間では、長年の付き合いから「ある程度の数量変更は融通が利く」という慣習が根付いていました。
ところが製品の需要急減という状況下、B社が急遽発注分の約半分をキャンセルすると、C社は通常仕掛品分や材料費、人件費を全て自己負担する羽目に。
契約書自体には「発注後のキャンセル時の対応」が何ら規定されていなかったため、C社側が損失補填を要求するも、B社は「これまでも臨機応変に対応いただいていた」と主張。
最終的に商工会議所の仲裁まで持ち込み、関係修復に膨大な時間と労力を費やす結果となりました。
品質基準の齟齬:阿吽の呼吸では済まされない
OA機器メーカーD社と鋳造部品サプライヤーE社のケースです。
過去の実績から、D社では“このくらいまでなら許容範囲”という独自の合否基準が社内では定着していましたが、E社には正式に数値基準を渡していませんでした。
お互い“察して”対応してきたのですが、市場でクレームが多発。
「検査や合格の基準が契約書や仕様書で明確化されていない」「慣習的ルールに基づいていた」という点が問題視され、調達部門と品質管理部門の双方で責任の押し付け合いとなりました。
最終的にはE社への賠償請求に至り、信頼関係は大きく損なわれてしまいました。
なぜ“取引慣行”がトラブルを招くのか?
製造業に根付く“昭和体質”の功罪
製造業では人と人との信頼、阿吽の呼吸、現場での臨機応変な対応が美徳とされてきました。
「お互い困った時は助け合う」「言わなくても分かるはず」といった昭和的な価値観は、確かにこれまで多くの現場で危機を乗り越えてきた原動力です。
しかし現代では、グローバル競争、法令遵守、リスク管理の重要性が高まり“あいまいな合意”や“慣行”は大きな足かせとなります。
ときに、その善意が誤解や不信へと変わり、ビジネスライクに厳格な線引きを求められる場面が増えています。
契約書の不備・曖昧さ=紛争リスクの温床
日本の製造現場でよくあるのが、テンプレート化された定型契約書、納期・数量・品質基準など、個別事情に十分対応できていないざっくりとした書面です。
サプライヤー側も、「取引停止を恐れて内容の交渉を避ける」「面倒なのでおまかせする」といった態度が見受けられます。
その結果、トラブル発生時に“契約書に書いていないこと=あいまいな領域”が抱えるリスクが一気に顕在化してしまうのです。
デジタル化の遅れが“見えない落とし穴”に
多くの現場では契約や商談記録が紙やExcel、口頭レベルで止まっており、デジタルで一元管理された情報が極めて乏しいのが現実です。
「誰と、どこまで合意したか」「いつ、どういう条件で合意に至ったか」が証拠として残っていなければ、双方の主張は水掛け論になってしまいます。
この“情報のブラックボックス”が紛争を複雑化、長期化させる大きな原因となっています。
紛争を未然に防ぐための5つの実践的予防策
<なぜ取引慣行が根強く残るのかを踏まえ、具体的な防止策を現場目線で解説します。>
1. 契約書(基本契約・個別契約)の内容精査とアップデートを徹底する
契約書を形だけの“おまじない”にしないために、現場の調達・購買担当者自身が「何がどう明記されているのか」「抜け落ちているリスクがないか」を自分事としてチェックします。
納期変更、数量変更、仕様変更、品質基準、キャンセル条件、損害賠償範囲、支払い条件など全項目を漏れなく点検し、できるだけ現場の運用実態との齟齬を減らしましょう。
社内弁護士や顧問とともに、実務現場の声をフィードバックし、定期的な見直し・アップデートを習慣化させることも重要です。
2. 主要取引の重要ポイントは「書面」「記録」で残すクセをつける
合意形成や契約変更など、“重要なポイント”は必ず書面やメール、社内システムなどで双方が証拠として残します。
現場の忙しさや「今さら文書化?」という心理的ハードルは高いですが、トラブル発生時の命綱になります。
できればクラウドなどデジタルプラットフォームで一元管理できる体制づくりもおすすめです。
3. 取引先とのコミュニケーション頻度と質を高める
たとえば四半期ごとの振り返りミーティングや、仕様・基準・慣行についての意見交換会、双方でのケーススタディ検討など、相互理解を深める場を意識的に設けましょう。
ここで「うちら流のやり方」「暗黙のルール」ではダメだという認識を一緒にもつことが、信頼関係の再構築につながります。
4. “最悪の事態”を想定したケーススタディ訓練を実施する
社内外で、「こういう事案が起きたらどう判断するか」「最悪の事態をどう乗り越えるか」を定期的にシミュレーションし、現場視点の知恵を結集します。
サプライチェーン全体を巻き込む大きなトラブルでは、誰が、どのタイミングでどう動くべきか、責任分担や初期対応フローなどを整理しておくことが重要です。
5. デジタル化による証跡管理の徹底と未来志向の改革
AI・RPA・ERPなど各種ITツールを積極導入し、契約書や仕様書、メールやプロジェクトの進捗記録もしっかりデジタルアーカイブ化していくべきです。
これによって属人的な記憶や“言った言わない”リスクを激減させ、未来の紛争予防につなげられます。
サプライヤーの立場でバイヤーの“本音”をどう読むか
しばしば「バイヤーは一方的な条件出しで冷たい」という印象を持たれがちですが、実情としては彼らも上司や経営層からの厳しいコスト・納期プレッシャーの間で板挟みになっています。
バイヤー側も本当は、「サプライヤーとの信頼関係を維持したい」「現場でトラブルを減らしたい」と思っています。
サプライヤー視点で重要なのは、単に契約を飲み込むのではなく、実務上守れない要件や、曖昧なルールがあれば勇気をもって質問・交渉する姿勢です。
「現場はこう動いている」「過去こういったトラブルがあった」と具体例を交えて会話することが、“言外の不安”“お互いのモヤモヤ”を見える化し、相互理解につながります。
今後の製造業に求められる契約・リスクマネジメントの姿
グローバル化、少子高齢化人材不足、災害リスクの高まり、新型コロナウイルスのような不測の事態——。
これからの製造業では、現場の小さな“習慣”ひとつが置き去りになっただけで、全社レベル・業界レベルのトラブルに発展する時代です。
昭和から続く“慣行”は大切に守りつつ、それを「書面」「デジタル」「明文化」で補強し、時代に即したアップデートを意識しましょう。
この“ラテラルシンキング”こそが、未来の製造業を支える新たなスタンダードになるはずです。
まとめ:未来志向の“現場知”が製造業を変える
契約書に明記されていない“取引慣行”が紛争の火種になる——。
この現象は今も多くの現場に根強く残っている問題です。
ですが、ちょっとした工夫と現場の気づき・コミュニケーションの積み重ねで、ほとんどのリスクは回避できます。
現場目線の実践力と、デジタル・法務の知見をバランス良く掛け合わせた“新しい地平”を開拓し、製造業の現場価値を進化させていきましょう。
今日からできる小さな一歩を、ぜひあなたの現場でも実践してみてください。