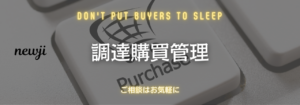- お役立ち記事
- 関税評価でのロイヤルティ加算漏れに起因する追徴と遡及の回避手順

関税評価でのロイヤルティ加算漏れに起因する追徴と遡及の回避手順

目次
はじめに:関税評価の基礎とロイヤルティ問題
関税評価の現場では、「何をいくらで輸入したか」という取引価格だけに意識が向きがちです。
しかし、知的財産権や商標権、技術供与などの「ロイヤルティ(使用料)」についての認識が十分でないと、税関による追徴や過去分の遡及課税といった重大なリスクを招きかねません。
昭和のアナログ体質が根強く残る業界では、購買現場が「型どおり」契約書を発行しても、実態を正しく把握せずに見逃してしまうケースが後を絶ちません。
この記事では、実際の製造現場で直面する「ロイヤルティ加算漏れ」による関税リスクを防ぎ、追徴課税と遡及リスクから自社を守るための具体的な手順とポイントを、現場管理職・バイヤー・サプライヤーのそれぞれの視点も織り交ぜながら解説します。
関税評価におけるロイヤルティとは何か
ロイヤルティ加算の背景
WTOや日本の関税法では、原則として商品の輸入取引価格が関税評価額となります。
しかし、実質的な商品の対価の一部である「ライセンス料」や「技術提供料」も、一定の要件に当てはまる場合は関税評価額に加算しなければなりません。
具体的には、輸入貨物に「直接または間接に」関連する下記のような費用です。
– 商標権や特許権の使用料(ロイヤルティ)
– 輸入元や第三者への技術指導・技術ライセンス料
– 設計費や開発費の一部
これらを見逃し、「カタログ記載の本体価格(CIF)」だけを申告していると、税関の事後調査で「本来加算すべきロイヤルティが抜けている」と判定される危険が高まります。
業界でよくある「ロイヤルティ加算漏れ」の事例
– 製造設備の導入時、取引先から提供されたノウハウ料が本体価格に含まれていなかった
– OEM製品の調達で、技術ライセンス料(設計図供与料)の申告漏れ
– 商標権使用料を「別契約」にしていたため通関書類から漏れた
これらはどれも、関税評価ガイドラインに照らすと「加算対象」に該当する場合が多く、後からまとめて追徴されるケースが目立っています。
なぜロイヤルティ加算漏れが起きるのか?現場視点の原因分析
複雑化する契約形態と断片的な情報共有
多くのバイヤーは調達コスト低減を最優先課題にしています。
そのあまり、価格交渉や品質管理には細心の注意を払うものの、契約書のロイヤルティ条項や、技術料・設計費・商標権料の内訳にまで目が届かないことがしばしばあります。
サプライヤー側もビジネス慣行上、「ロイヤルティ」項目をできるだけ外部に分離し、本体価格を安く見せたい心理が働きます。
また、日本本社から海外子会社や取引先へのライセンスフィー支払も、経理部門と調達購買部門で認識がずれている場合もよく見受けられます。
昭和由来の「前例踏襲」志向
製造業の現場に根付く「過去と同じやり方で問題なかった」という意識も、ロイヤルティ加算漏れの温床になっています。
事務手続きが複雑化するほど、「前年度と同じ納入条件」「前年踏襲の通関書類でOK」となりがちだからです。
追徴と遡及課税の実態〜現場でよくあるパターン〜
税関によるロイヤルティ漏れの指摘例
税関の事後調査は数年ごとにランダムに入ります。
その際、社内の会計帳簿や契約書一式が精査され、「なぜ設計供与費や商標利用料を本体価格と別処理しているのですか?」と具体的に質問されるのが通例です。
仮に過去5年間でロイヤルティ加算漏れが見つかると、その期間分の差額・遅延税が一括して追徴されます。
遡及が招く経営インパクト
– 数千万円〜数億円規模の「思わぬ特損」となり、決算に悪影響
– 経理・調達部門の担当者が「重大なコンプライアンス違反」に問われる
– サプライヤーとのトラブルや追加コスト交渉に発展
特に上場企業や大手グローバルメーカーでは、J-SOXや内部統制の観点からも「関税評価リスク」を放置できなくなっています。
ロイヤルティ加算漏れを防ぐ実践的な手順
1. 契約プロセスの見直しと関税評価の事前把握
最も重要なのは、商談や契約締結時に「関税評価額」の観点からロイヤルティの取り扱いを明確にすることです。
– ライセンス契約、技術提供契約、商標権付与契約などは購買担当者・経理担当者・通関担当者全員で内容精査を行う
– 輸入品に関連する付帯的な費用(設計図供与料、特許権料等)も「本体価格と一体不可分なら加算対象」と意識する
2. 社内体制の横断的な連携強化
– 購買部門だけでなく、経理・法務・通関など複数部門による「クロスチェック」をルーチン化
– 新製品の本格生産や新たな取引開始時には、事前に税関当局や専門コンサルタントへ諮問する体制作り
3. 書類管理とエビデンスの精度向上
– 契約書類・費用内訳書は紙・データ両方で体系的に保管
– サプライヤーとのメールや会議ログにも「ロイヤルティ条項」が含まれていればアーカイブ化
– 外部監査・税関監査を想定した「説明責任」が取れる体制を構築
4. 税関との積極的なコミュニケーション
過去の遡及を恐れるよりも、グレーな事案は申告前に税関や専門弁護士へ事前相談するのが有効です。
「判断が難しいけれど念のため確認したい」と正式に照会することで、後の追徴リスクや意図せぬ誤解を防げます。
サプライヤー・バイヤー双方の信頼関係構築がカギ
サプライヤーの立場でも「バイヤーが関税評価に神経質になっている背景」を理解し、誠実かつ透明性の高い商談を心掛けることが肝要です。
逆にバイヤー側も、費用項目ごとに明細化を求めるだけでなく、サプライヤーと一緒になって「何が関税加算の対象か」を細かく仕分け、トラブル未然防止に努める姿勢が求められます。
まとめ:現場力とラテラルシンキングで「防衛線」を築く
関税評価におけるロイヤルティ加算漏れのリスクは、現場一人ひとりの意識と部門横断のチームワークによって大幅に減らせます。
昭和のアナログ時代の感覚に留まらず、「一歩先を読む現場調査力」と「問題を水平展開して考えるラテラルシンキング」が今後ますます求められます。
特に調達購買・生産管理・品質保証・経理・法務といった多様な職種が連動し、サプライヤーともオープンに課題共有することが、現代ものづくり企業の競争力向上=経済的な防衛線につながります。
この記事でご紹介した手順やポイントを土台に、自社ならではの「関税リスク管理マニュアル」をぜひ作り上げてみてください。
現場目線の小さな工夫の積み重ねが、将来の大きな企業の成長と利益を守るのです。