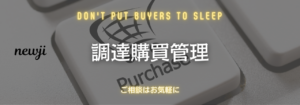- お役立ち記事
- 機械・構造物の経年劣化・損傷原因究明と適切な対策および余寿命評価への活かし方

機械・構造物の経年劣化・損傷原因究明と適切な対策および余寿命評価への活かし方

目次
はじめに:製造業の現場が直面する「経年劣化」のリアル
機械設備や構造物の経年劣化、損傷は、ものづくりの現場にとって避けて通れない重大な課題です。
日本の製造業は、高度経済成長期に導入した設備や建屋が今なお現役で稼働しているケースも多く、「昭和遺産」とも言える装置たちが支えている現場は少なくありません。
しかし、老朽化に起因する事故・トラブルは生産性や安全性、さらには企業の信用をも脅かします。
また、アナログ色の強い文化が根強く残り、紙ベースの管理や経験則頼りの判断が主流の会社も依然多い状況です。
本記事では、20年以上にわたり製造業の最前線で培った現場目線で、経年劣化・損傷の原因究明のノウハウ、実効性ある対策、そして近年注目される余寿命評価のポイントについて、深く掘り下げます。
バイヤーや生産管理、品質管理業務に関わる方、さらにサプライヤーの立場の方にも今後の“勝てる現場”づくりに役立つ内容を具体的にお届けします。
経年劣化・損傷の真因とは:「なぜ、それが起きるのか?」を掘り下げる
1. 経年劣化のメカニズムを理解する
まず重要なのは、「劣化=すべてが摩耗していく単純な現象」ではないということです。
現場では、摩耗や腐食、疲労、割れ、変形といった表面的な現象にばかり目がいきがちですが、その背後には必ず「何かが引き起こす根本原因」が存在します。
例えば、以下のようなケースがあります。
– 設計時の安全係数不足や材質不適合による慢性的過負荷
– 周囲環境(湿度、温度、薬品雰囲気等)の未考慮
– 点検・保守の方法や周期の不備
– 作業員の運用手順逸脱や技能格差
– 市場や稼働状況の変化による設備の設計前提逸脱
つまり、経年劣化という言葉の裏には、「想定外でルールが形骸化した運用」「人、設備、情報のサイロ化」「個人に依存したブラックボックス化」など、組織の“昭和的課題”が潜みやすいのです。
2. データと現場の「生きた声」両面からアプローチする
経年劣化や損傷を真に解明するには、物理的現象の観察だけでなく、「現場で何が本当に起きているか」を知る必要があります。
– 「思い込み」や「慣例」を疑う現場ヒアリング
– 経年変化による機械振動・異音・温度・電気特性の長期測定
– 定期・非定期メンテナンス時の分解検証
– 故障履歴やメンテ記録の”見える化”
– 過去トラブル時の5WhyやFTAなどのロジカルな原因分析
アナログ現場では、“あの人なら状態が分かる”“カンで分かる”とされがちですが、属人的な知見に頼るだけでは、多様な原因が絡み合うトラブルの根絶は難しいです。
データ記録を習慣化し、過去のトラブル教訓を部署や世代を超えて共有できる環境づくりが、本質的な要因究明の一歩となります。
現場に根付く「昭和マインド」から抜け出すには
1. 形式主義・属人化を打破する「仕組み」作り
日本の製造業現場で今も根強く見られる課題に、「勘と経験の継承」「属人化した職人技のブラックボックス化」「報告書だけの形式主義」があります。
これらを乗り越えるためには、以下のようなアクションが効果的です。
– 点検・保守記録を“紙”から“デジタル”へ電子化
– “ヒヤリハット”や“小さな異常”を一元集約し全体最適化
– 不具合時は部門横断で本質原因を掘り下げ解決策へ
– 失敗・異常事例も「オープンに議論できる」文化の醸成
DX(デジタル・トランスフォーメーション)が進む昨今ですが、真のDXは道具を入れることではなく、「人と情報とノウハウをつなぐ仕組み作り」そのものにあります。
2. バイヤー・サプライヤーこそ「余寿命管理」という新たな付加価値
バイヤーや生産管理の担当者は、単なるコストと納期だけでなく、サプライヤーと連携して「設備・構造物の余寿命」を戦略的に把握し、投資や更新計画を立てることが求められます。
サプライヤーの側も、保守メンテナンス履歴や材料特性のデータ提供、技術提案型サービスによって差別化が可能です。
日本のアナログ現場では、こうしたサービス連携がまだまだ浸透しにくい傾向にありますが、「長期間、安心して動き続ける商材」を提供できれば価格競争に巻き込まれない新たなパートナーシップ構築が成り立ちます。
実効性ある「経年劣化・損傷」対策の進め方
1. 日常点検と予知保全の”レイヤー設計”
まずは「壊れてから直す」ではなく、「壊れる前に手を打つ」体制づくりが基本です。
– チェックリストの見直し(何を見て、どう判断するか)
– 作業者レベルで分かりやすく、かつ短時間で実施可能な体制
– 定量的な基準値・しきい値(温度・振動・音など)設定
– IoTセンサー活用による遠隔監視・自動警報
現場レベルの“いつもの点検”と、上位層(工場管理者、経営者)による「余寿命の見える化・更新計画」の両輪で仕組みを回すことが必要です。
2. トラブル再発防止と「根本原因解決」
不具合や損傷が発生した場合は、
– なぜ再発したのか
– 同種の設備で発生するリスクは?
– 現場の声や作業内容にどんな改善余地があるか
を横断的に議論する仕組みづくりが肝心です。
属人的な「応急処置」だけでは真の再発防止にはなりません。
– 不良現象ごとの“兆候例”と“再発防止対策集”の作成
– 他部署や協力会社、バイヤーとの情報共有会議の継続
など、「ナレッジの横展開・標準化」が製造業全体の底上げにつながります。
3. 教育・OJTによる「気付き力」「異常感知力」の育成
昭和的現場では、熟練者の“見る目”“触った感覚”で初期トラブルを察知してきました。
デジタル技術やセンサーでの補助は重要ですが、現場感覚をそぐことなく次世代に継承するOJT、ケーススタディ研修の仕組みが不可欠です。
– 若手への「異音や振動」「発熱」「油量・色・匂い」など異常の気付き研修
– 失敗事例・過去トラブルの“リアルな教訓”の共有
– VRや動画教材、シミュレーションを活用した体験型教育
これにより、現場が自分ごととして「なぜ、異常が起きるのか」を理解し、現場力向上に結びつきます。
余寿命評価—“攻め”のメンテナンス戦略へ
1. 余寿命推定の基本アプローチ
設備や構造物の余寿命推定(RUL:Remaining Useful Life)は、「本当にどこまで現場で使えるのか?」という投資判断の核心となります。
基本的アプローチは以下のとおりです。
– 点検・保守履歴からの累積ダメージ評価(疲労、摩耗、腐食など)
– 過去トラブルとの傾向分析(AIや機械学習も活用)
– メーカーや規格値だけでなく、“現場実態に即した評価”による寿命予測
– 必要に応じてNDT(非破壊検査)、サンプリング解体による劣化確認
単なる目安や経験則ではなく、データに基づいた「定量的な根拠」と「現場ならではの勘と客観性」を掛け合わせることがポイントです。
2. バイヤー・調達視点の「コスト最適化」と余寿命の関係
余寿命評価を活用することで、次のような取り組みが可能となります。
– 安易な全数更新・不要な予防保全から“使い切り戦略”への転換
– 壊れる前に適切な時期で投資・入れ替えの計画立案
– サプライヤーと連携した「新しい保守契約」や「IoTメンテナンスサービス」導入
バイヤーは単なる購買の枠を超えて「リスク最小化」と「持続的価値提供の最適化」をリードする役割へと転換することができます。
まとめ:経年劣化対策は“現場主義×データ活用×人の力”の掛け算で
経年劣化・損傷・余寿命評価は、単なるメンテナンス管理の枠を超え、工場・設備のトータルな「価値創造活動」と捉えるべきです。
昭和的なアナログ管理だけでは、真の原因究明や持続的な競争力維持は難しい一方、現場のリアルな知恵や気付き力、歴史ある経験値もDXの土台となります。
– 属人化・形式主義の打破、現場参加型の本音主義
– バイヤー、サプライヤー、現場が一体となった付加価値の高い連携
– データ駆動型・見える化・余寿命管理による“攻め”のメンテナンス戦略
これらを実践することで、真の「現場力」が鍛えられ、持続的発展を遂げることができるのです。
アナログとデジタルの最適融合。昭和マインドから一歩抜け出し、現場から未来を変えていきましょう。